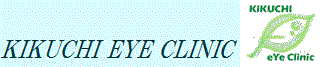コラム集 続スマホ内斜視 2025.10
以前「スマホと内斜視」というコラムを書きました。いわゆるスマホ内斜視です。まずはコラム「スマホと内斜視」(2019.06)をぜひご覧ください。
2016年に韓国からスマホの過剰使用で急性内斜視が発症したという報告がでて、日本でも2018年に同様の症例が報告されました。
その後多くの症例が示されたのですが、「使用時間」「視聴距離」「発症年齢」「改善するかしないか」などどうすれば内斜視の発症を予防・改善できるかに関してはまだよくわかっていない状況でした。
そこで日本小児眼科学会と日本弱視斜視学会が共同で多施設での研究を行いました。
第1報ではスマホ内斜視発症から1年以内の患者さんを小児(12歳以下)、中高生(13~18歳)成人(19歳以上)に分けて分析しています。
・患者数は16歳男子を中心として中高生に多い。
・左右の眼で近視や遠視などの屈折度数の差が大きかったり、斜位(斜視ほどではないが軽く目の向きにズレがある)など、元々両眼視機能が不安定な人が内斜視を発症しやすい。
ということでした。面白いことにスマホがない1995年に行った少数例での調査も、急性内斜視を発症した年齢分布と斜視角の程度はこの研究結果と類似していたようです。
受験に対するストレスと、受験のための長時間の近見作業(受験勉強)が原因ではないかとの結論でした。
第2報ではスマホ使用時間に注目し、非過剰群(小児1時間未満、中高生と成人は2時間未満)
とそれ以上スマホをみている過剰群に分けてスマホ視聴の指導に対してどう変化したかを検討しています。
指導内容はスマホを少なくとも30㎝以上離してみること、30分の視聴後に5分の休憩時間を入れること、スマホの視聴時間を非過剰群のレベルに控えることです。
その結果は過剰視聴群は平均262分から179分に減少し、全体としてはわずかながら内斜視の程度が良くなり、3か月後に治癒に至った症例もありました。
第3報は過剰使用群のみを対象とし、第2報で紹介した指導を守った3か月間後に治癒、改善、不変、悪化の4群に分けて検討しました。
・治癒、改善には初診時に内斜視の程度が軽く立体視が良好であることと、スマホ視聴時間を初診時の半分以下に減らすことが重要である。
・スマホを視聴しても内斜視にならない安全な視聴時間があるわけではなく、各個人で安全な視聴時間は異なる。
・いったんスマホ内斜視を発症するとデジタル機器の使用時間を制限しても治癒するのはごく軽症の時に限られる。
両眼視機能が発展途上である小児では、内斜視がひどくなっていない軽症の時に早期発見し早期に治療することが必要です。 スマホ内斜視にならないように是非ご家庭で子供さんのスマホ使用法について話し合ってみてください。