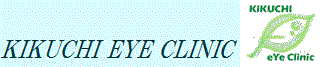コラム集 生活環境因子と緑内障 2025.01
前回のコラムで紹介した、ユーチューブの動画を見てゴリラに気づいた方は少なかったのではないかと思います。 私も気づきませんでした。 医療専門学校の視能訓練士科に講義に行く機会があるのですが、講義に先立ち学生さんたちにこの動画を見てもらっています。 ほとんどの学生は気づきません。教室で多くても数人、誰も気づかないことも珍しくありません。 非注意性盲目といって、注意を払っていないことには気づかないという現象です。 スマホを見て運転したり歩いたりしている方が本当に多いのですが、歩行者を見ているつもりでも、そばにいる子供や持っているキャリングケースに気づかない可能性があります。 その後ろからくる自転車やほかの対象を見落としているかもしれません。とにかくながらスマホはやめてください。あなたが思っている以上に大変危険な行為です!
今回から運動・食事・睡眠などの生活環境因子と眼の病気について考えていこうと思います。
長寿社会になり、いかに健康寿命を延ばすかということが課題になっています。
眼科では緑内障、白内障、黄斑変性症などの慢性疾患の予防や、進行を抑えるための生活習慣の改善が重要になってきています。
眼の病気で一番生活環境因子が大きく影響するのは糖尿病網膜症でしょう。
糖尿病の管理をしっかりしていただけないと眼だけでなんとかしようとしても限界があります。
今回は緑内障についてです。網膜神経節細胞が障害される緑内障には大きく分けて2つあります。
開放隅角緑内障(POAG)と閉塞隅角緑内障(PACG)です。PACGは閉塞している隅角を開放するということが治療の第一選択です。
POAGは点眼で眼圧を下げる治療を行います。緑内障の多数を占めるPOAGの発症予防と進行の抑制についていくつかの生活環境因子が関与していることが示唆されています。
・喫煙
世界保健機関(WHO)からPOAGの発症、進行に寄与する可能性があると警告されています。喫煙は本当に百害あって一利なしです。
・睡眠
睡眠時無呼吸症候群がリスク因子であることがわかってきました。
原因は明らかになってはいませんが、無呼吸が引き起こす低酸素や虚血が影響しているのではないかと考えられています。
・運動
上2つはリスク因子ですが、運動は抑制因子です。
有酸素運動がPOAGの進行を抑制するという報告がされています。神経保護因子の上昇や循環血流量の増加が網膜神経節細胞に保護的に働くそうです。
ある研究では1日当たり5000歩くか、座っている時間を2.6時間短くすると、視野欠損の進行が約10%抑制できることが分かったそうです。
眼圧を下げることに関しても運動はいい影響を与えます。
特に運動不足の人が運動を行うことで眼圧が大きく低下するそうです。このように運動は緑内障予防と進行抑制の両方にいい影響を及ぼします。
私は緑内障患者さんには「緑内障は基本的には生活習慣病ではないのであまり普段の生活について気にする必要はないです。」とお話ししていますが、もし運動不足が日ごろから気になっている方は適度な運動を心がけるのもいいかもしれません。
余談ですが、適度な運動は体だけではなくうつ病の改善など精神的にもいい影響を及ぼしてくれます。